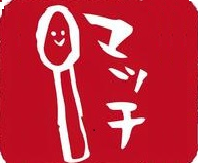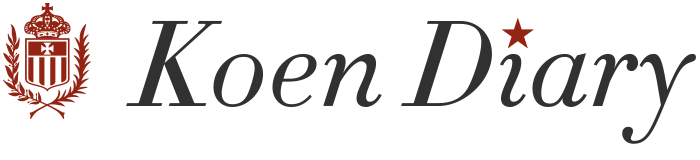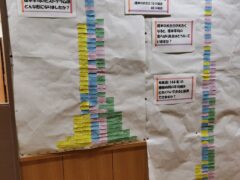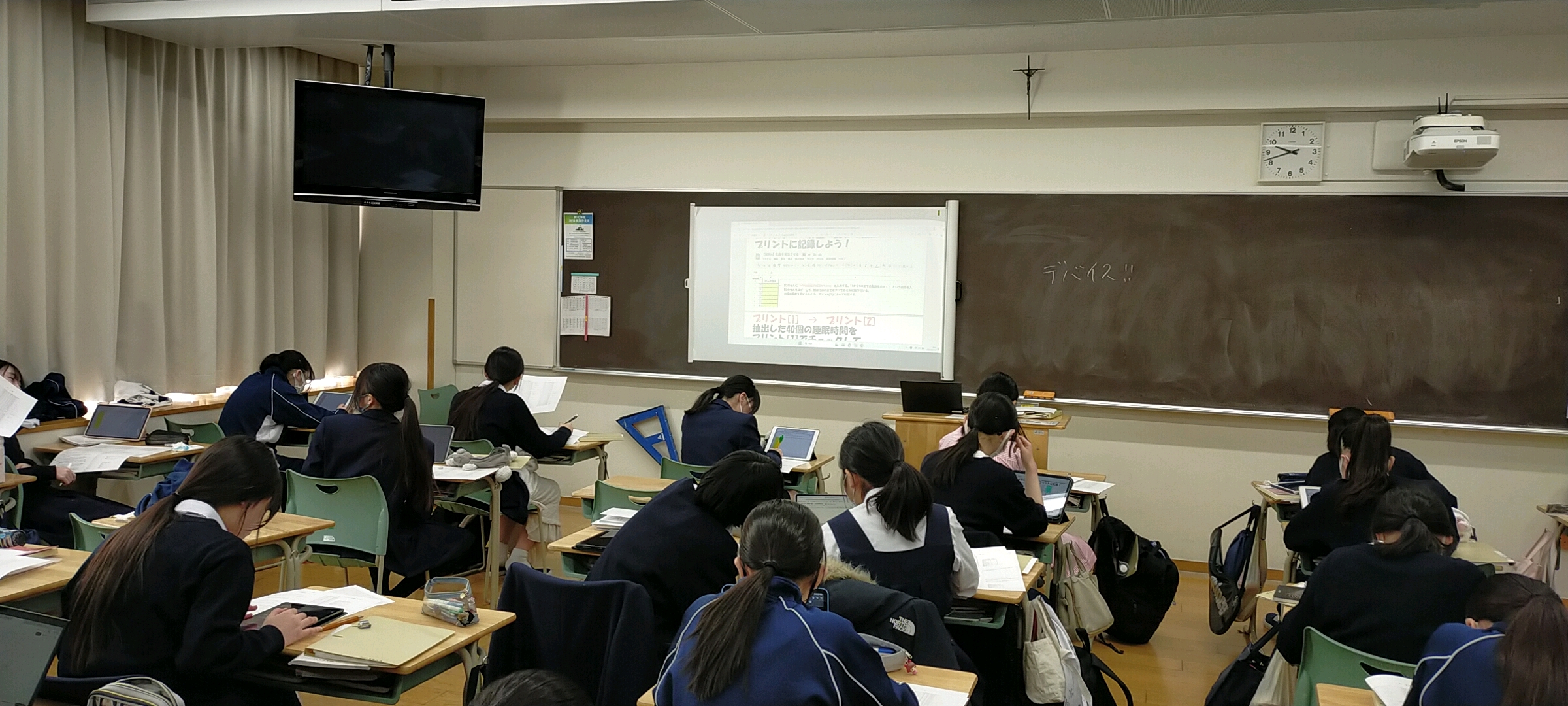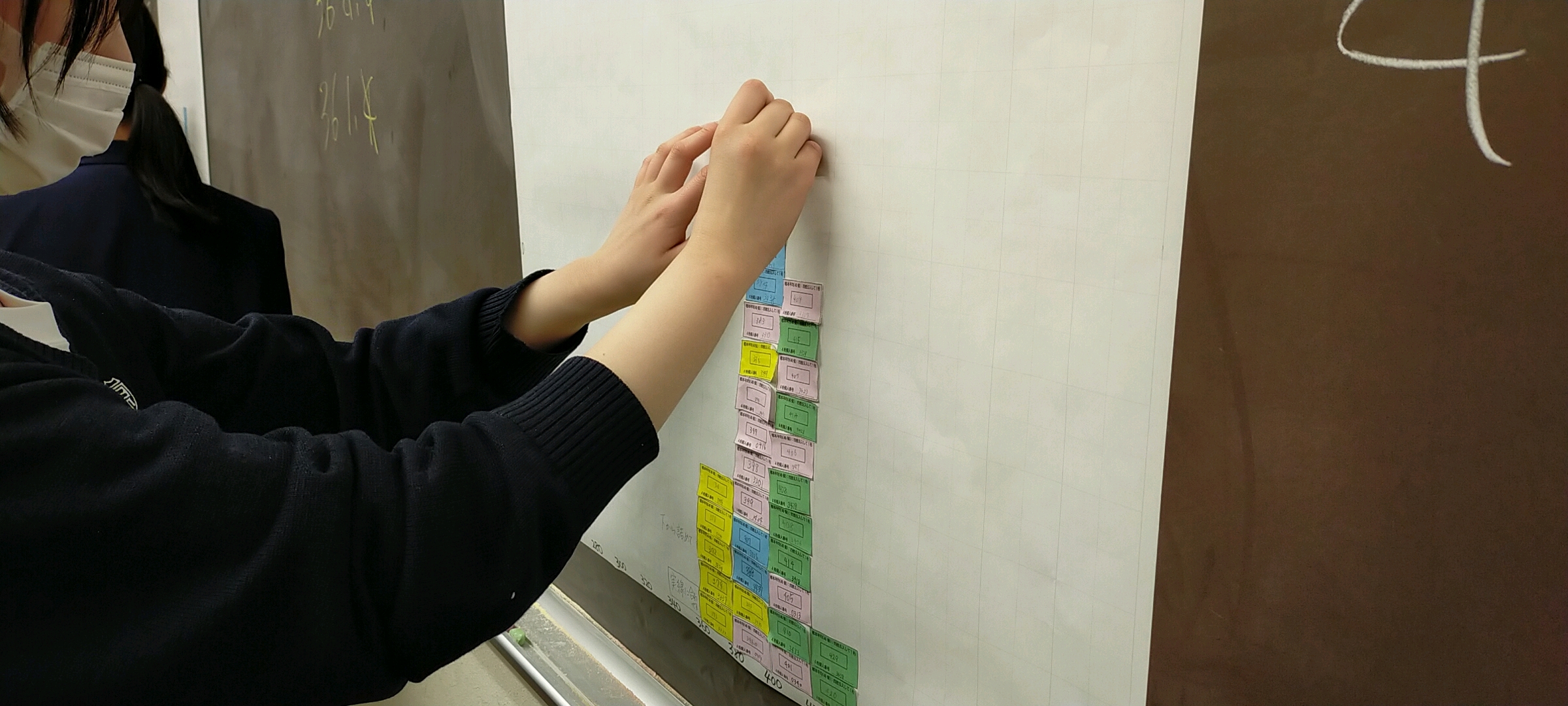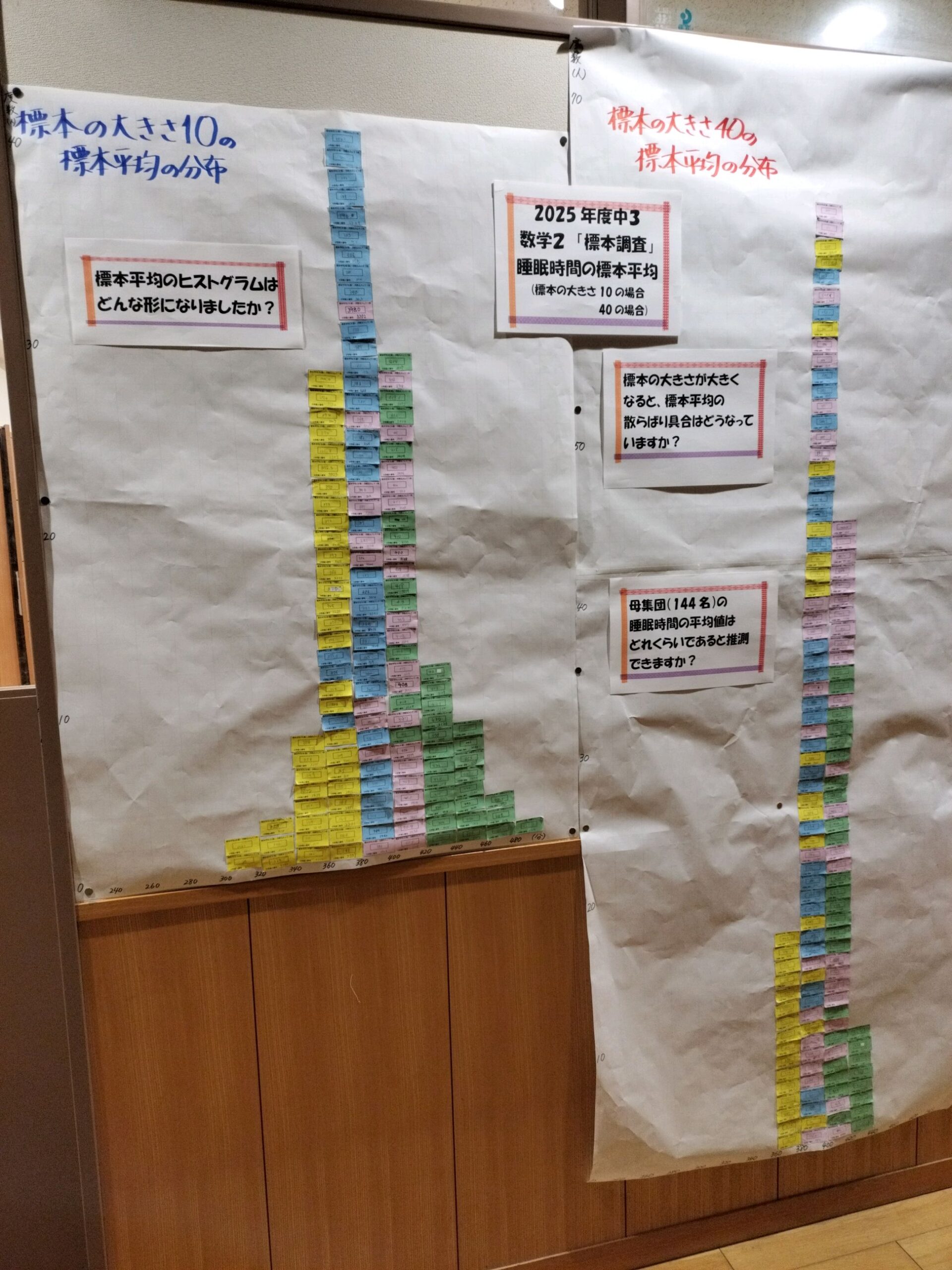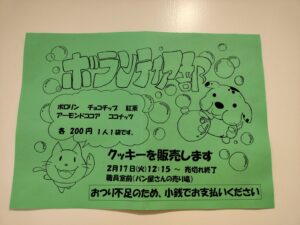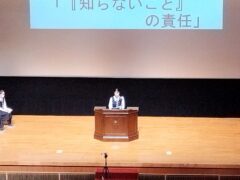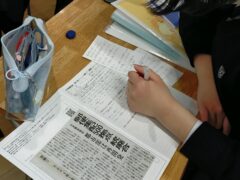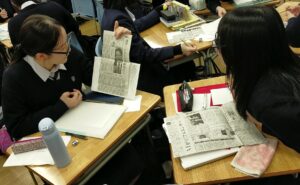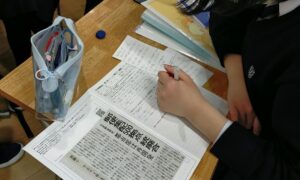高等科 3 年 稲垣こころさんが、第71回青少年読書感想文全国コンクール(高等学校の部・自由図書)で文部科学大臣賞を受賞しました。
以下に、全文を掲載します。
タイトル:「愛の河」(遠藤周作『深い河』の感想文)
神は、存在するのだろうか。
神とは、立ち直れないほどの悲しみに見舞われた人が、救いを求めて信じる存在であり、信仰とは、人智を超えた絶対的な力を信じて縋ることだと、そう思っていた。
その考えを変えたのは、大津と美津子だ。
神父を志す大津は、その汎神論的な考えで教会の顰蹙を買い、今はインドに住み、瀕死の人や、誰にも火葬してもらえない遺体をガンジス河に運んでいる。大津と同じキリスト教の大学に進学しながらも、西洋の神に偽善を感じていた美津子は、本当の人生を探すためにやって来たインドで、彼と再会する。
大津は、転生を信じてガンジス河にやって来たヒンドゥー教徒を背負い、死にゆくその人と共に悲しみ、祈っている。その行動は、彼の生活に何の恩恵ももたらさないし、貧困に喘ぐインド人を減らすわけではない。では、大津の人生は無意味なのだろうか。大津の存在は、無力なのだろうか。
私は一つ、気づいたことがある。それは、大津は自分の人生に意味を見いだしているということだ。彼は西洋の修道士や、美津子に馬鹿にされながらも、自分より大きな存在に生かされていることを実感している。
その姿は、人生の意義を見失ってもがく美津子の、そして彼女に深く共感した私の人生と対照的である。例えば、友達と他愛ない話で大笑いして別れた後、一人で電車を待っている時。何気なくつけたテレビに、飢餓に苦しむ難民の子供たちが映った時。唐突に、形容しがたい不安に駆られることがある。何のために生まれてきたのか、訳もなく考えてしまう。結局何も為さないまま、人生を終えるのではないか、という漠とした絶望に襲われることがある。なぜだろう。
その答えは、ガンジス河が教えてくれた。焼いた死体の灰を流す、聖なるその河は、流した人生の分だけ濁りながらも、まるで人間など意に介さぬように流れ続ける。苦しむ人々の叫びが聞こえぬかのように回り続けるこの世界と同じように、沈黙したままなのだ。まだ見ぬガンジス河を想像したとき、私は、美津子と私、そして大津に運ばれていく人々の底を流れる「人間の悲しみ」に気付いた。
それは、生かされていることの必然性を失った悲しみである。いつの間にか生まれ、人生の如何に拘らず、やがて死ぬ。この普遍的で絶対の運 命に規定された私たちは、自らの力で「生まれてきた意味」を獲得しなければいけない。実生活の営みの中に埋没しているときは、ただ生きることは容易いし、肉親や夫婦の繋がりの中に、人生の意味を見いだすこともできる。でも何かのきっかけで、 他の誰とも分かち合えない、孤独な自分と対峙せざるを得ないとき、人は人生の同伴者としての神を、知るのだと思う。
その神は、純潔の聖母マリアかもしれないし、醜く老い果てたチャームンダー女神や、すり減って歪んだ踏絵の中のキリストかもしれない。私はまだ、自分の中に在る神の輪郭は得ていないが、『深い河』を通して、人生の同伴者としての神の存在を、確かに感じた。
神は、人間が救い主として創造した存在ではなかった。私たち一人一人の心の中にはじめから存在していて、根源的には孤独な私たちと、いつも共に在るのだと気付いた。信仰心は、救われたいという特定の目的によって得られるものではなかった。人生の意義を疑ったとき、自分に最も近いところに佇み、沈黙している神の存在を感じることによって得られるものだった。無力ながらも生き続けている私たちは、それぞれが人生の悲しみを背負っている。でもその悲しみは同時に、私たちは確かに生きている、生かされているという実感に裏打ちされたものだ。神による救いとは、そんな私たちに寄り添い、共に悲しんでくれることなのではないか。
大津は無力かもしれないが、確かにこの世界を生き、彼の神と共に、 苦しむ人々に寄り添ったのだ。大津が人生の同伴者として見いだしたのは、私が最初に想像していたような絶対的な力を持つ神ではなかった。キリスト教の神とも言い切れない大津の神は、しかし決して、不完全な大津を見捨てない。彼が信じる神は、 愚直で弱い大津に、生かされている意味を教えてくれた。
そして大津は、美津子に、彼女自身の中にも神がいることを教えたのだ。美津子が自分の無力さを噛みしめているとき、神もまた、美津子と共に苦しんでいる。生かされていることの意味を時には見失いながらも、人生を歩み続ける人間の側に、いつも神はいる。
そう気付いたとき、私には遥か遠くのガンジス河が、確かに人間と共に在る神の、深い愛の河に見えた。 数多の人生、数多の悲しみを包み込みながら、ただ流れていくガンジス河のように、神の愛は、私の人生に寄り添いながら、いつも、ただ、そこに在る。