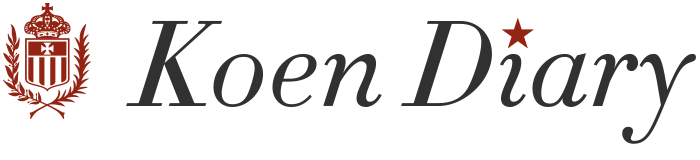光塩生のための「建築ガイダンス」~矢野裕之先生をお迎えして~ 光塩生のための「建築ガイダンス」~矢野裕之先生をお迎えして~
「建築」=”architecture”とはそもそも何でしょう?buildingではありません…光塩生のための「建築ガイダンス」はこんなお話から始まりました。この企画は、すいどーばた美術学院建築科の矢野裕之先生をお迎えし、建築学科を目指す生徒のため開かれたものです。5月13日、20人余りの希望者はラーニングコモンズに集まり、先生のお話に耳を傾けました。
最初の質問の答えは「一つの思想によって統合された空間(的)世界のこと」。例えば、東京カテドラルは、カトリックの大聖堂ではありますが、建築家丹下健三によって、日本人に馴染みのある空間のありようを探るようにして設計されたものなのだそうです。頭上を見上げれば十字架のトップライトから光が降りそそぎ、大聖堂の基本形に即して造られたことが分かります。しかしその空間の全体像は山を思わせるシルエットになっていて、一般の大聖堂とは大きく異なっています。古来、日本には、例えば浅間信仰に代表されるように、大きな山に向かって手を合わせるという祈りの姿がありました。そうした印象を与えようと、まるで富士山のような曲線のシルエットをもった祈りの空間となっているのです。
それでは、大学の建築学科は何を学ぶところでしょう。矢野先生は、建築学科のうち計画系・構造系・環境系それぞれの研究分野について、数十年先の未来を探り、時には地球規模の視点を持つものであることを、タワーマンションによる大規模開発が招く地域の変化や「宇宙船地球号」の概念を提唱した建築家・バックミンスター=フラーを例に分かりやすく話してくださいました。
工学系と芸術系の建築学科の違いの背景にある、科学知と生活知という異なった学問体系や、建築計画で必要となる“思想”、さらに大学の入試の実技試験に込められた狙いの説明に続いて、「ここにあるような本を読むのが大切なんですよ」とラーニング・コモンズの棚を指さされた先生の言葉に、はっとした生徒もいたようです。
矢野先生ご自身のお仕事や豊かなご経験を交えたお話に、生徒からは質問が止まらず、会の終了後も先生を囲んでメモを取りながらお話を伺っている姿が見られました。建築を目指す生徒にとって、貴重なガイダンスとなりました。

参加した生徒からは「今からできる、デザインする力や建築に関する知識を増やす方法はありますか?」「設計する上で、矢野先生が大切にされていることは何ですか?」と質問が相次ぎました。

矢野裕之先生。ローマのパンテオンから現代日本まで、さまざまな地域や時代の建築を例に、建築学の魅力を話してくださいました。